円安のメリット5選とデメリットの対処法5選!
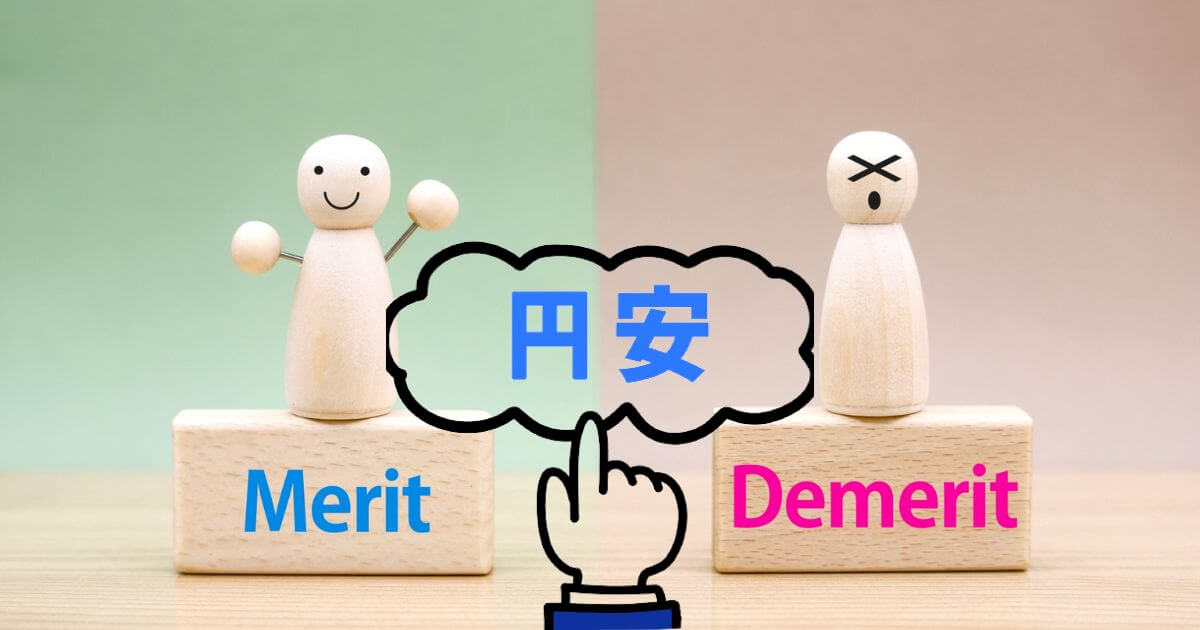
円安とは、円の価値が下がることを意味します。
たとえば、アメリカに旅行するとしましょう。円をドルに換金するとき、今までの旅行では1ドルあたり100円だったのが、今回の旅行では130円でした。この場合、円を30円多く出さなければ1ドルと換金できなくなったわけですから、ドルに対する円の価値が下がっています。この状態を「円安が進行している」といいます。
本記事では円安が進行しているいま知っておきたい、円安のメリット5選とデメリットの対処法5選を解説します。
もくじ
円安のメリット5選
円安が実生活にもたらすメリットは、次のとおりです。
- 海外の株式を購入するきっかけになる
- 海外の方向けに不用品やハンドメイド商品を売れる
- 賃金が上がる場合がある
- 外国人と友人や恋人になりやすい
- 不動産の売却益を得やすい
海外の株式を購入するきっかけになる
アメリカなどの海外企業へ投資している方は、円安で利子や配当が増えやすい傾向があります。
たとえば、投資している米国企業から投資家に対して100ドルの配当があり、これを日本円に換金するケースを考えてみましょう。
1ドルが100円のときは、換金額は単純計算で1万円です。ところが、円安が進み1ドルが130円になっていたら、換金額は1万3,000円です。
同じ100ドルを受け取ったのに、換金のタイミングが違うだけで、3,000円もの差が出ます。
海外の方向けに不用品やハンドメイド商品を売れる
円安の状態は海外から見れば、日本の商品が安く買える状態です。海外のフリマサイトで不用品やハンドメイド品を出品することで、儲けが出やすい傾向があります。
アメリカ在住の方が日本の通販サイトなどから商品を購入したい場合、これまでは1ドルを払っても100円の商品しか購入できませんでした。
ところが、円安が進むと同じ1ドルを払っただけで、130円の商品が購入できるようになるのです。この現象を利用して、フリマサイトなどで安く日本の商品を購入したいと考える海外の方もいます。
不用品やハンドメイド商品をフリマサイトで販売した経験のある方は、これまでよりもお小遣いが増えるチャンスかもしれません。
なお、海外への配送については国際配送が必要になりますが、代理での転送サービスなども存在するため、外国語が分からなくても気軽に始められます。
賃金が上がる場合がある
お勤め先が輸出産業系の場合は、賃金が上がるケースがあるかもしれません。
輸出産業においては円安が進むことで、海外からの買い付けが通常よりも増えるケースがあります。この結果、通常時よりも利益が出やすくなるのです。
会社の利益が上がれば、その分、その会社で働く従業員の給料やボーナスがアップする可能性も出てきます。
外国人と友人や恋人になりやすい
円安は海外の方からすれば、うれしい時期です。この状況を利用して、日本に旅行する外国人の方が増えてきています。
外国人観光客が増えれば、バーやカフェなどで知り合うきっかけにもなり、連絡先を交換できることもあるでしょう。
外国人の方と交流を持つきっかけは、あるようでないものです。円安をきっかけに、新しい世界が広がるかもしれません。
不動産の売却益を得やすい
円安は、戸建てやマンションなどの不動産を売却し、売却益(不動産を売って得られるお金から、かかった費用を差し引いた金額)を得るときにも有利です。
国土交通省が2022年(令和4年)8月に公表した「不動産価格指数の資料」によると、不動産価格はマンションや戸建てなどの種類を問わず、年々高まりつつあります。
日本の不動産が円安によって割安になると、東アジア圏のみならず、英語圏からの不動産購入検討者も増加しました。
国内の買い手だけではなく、国外からも買い手が付くようになり「売り手市場」が形成されているのです。
円安の状況は、買い手が多く売却価格も高くなる傾向があるため、売却を検討している不動産がある場合は、円安の時期に見積もりするとよいでしょう。
円安のデメリットと対処法5選
一方、円安が続くことで発生するデメリットもあります。
以下では、円安のデメリットと回避するための対策法5選を紹介します。
海外旅行の費用が高くなる
海外旅行にかかる費用は、円安が進むほど高くなる傾向があります。現地のホテルや食事、レジャーなどのグレードを維持したい場合には、円安でない時期よりも、予算を上げる必要があります。
たとえば、1ドルが100円から130円になったと考えてみましょう。この場合、これまで1万円出せば、100ドル相当のサービスが受けられていたところを、1万3,000円出す必要があります。
対処法
円安かどうかは、その国で使われている通貨によって変わります。そのため、円安があまり進行していない国を選んで旅行に行くことで、予算オーバーせず海外旅行が楽しめます。
たとえば、2022年(令和4年)現在であれば、韓国(ウォン)やタイ(バーツ)は、円安の進行が比較的穏やかです。
国内の物価が上がる
円安の影響で物価が上がるのは、輸入品だけではありません。国産の製品も、円安の影響を受けて値上がりするケースがあります。
たとえば、家電などは生産拠点(工場など)を海外に移転している場合がほとんどですから、円安によるコスト増加の影響を受けやすくなります。
また、ティッシュやトイレットペーパーなどの日用品も、海外から原料を買い付けている場合は、製造コストが高まります。
また、円安によるガソリン代の増加も見逃せません。たとえ原料や部品をすべて国内で調達できたとしても、国内での輸送は避けられないでしょう。
結果として円安では、国内の物価が全体的に上昇してしまうのです。
対処法
物価の上昇で気になるのが、預貯金などの目減りです。預貯金の目減りを抑えるには、資産を現金ではなく「モノ」で持つことが重要です。
貴金属や不動産、株式や債券などの金融資産でももちろん構いません。しかし、貯金に余裕がないときには、なかなか新たな金融資産を購入するまでは手が出しにくいでしょう。そんなときは、食料品や日用品を「安いときに購入する」ことを心がけましょう。
たとえば、円安によって1袋500円になってしまったティッシュペーパーを、安売り時に300円で購入できたとしたら、それは「200円分の価値を生み出したティッシュペーパー」といえます。
小さな積み重ねで、モノを財産に変えていくのが重要です。
光熱費が上がる
日本は天然ガス、石油、石炭などの燃料を輸入に頼っているため、電気代やガス代は、円安時に大きく値上がりしてしまいます。
たとえば、2022年(令和4年)に東京電力が発表している、モデル家庭の電気代は、12月で9,126円です。しかし、1年前の2021年(令和3年)時は7,485円のため、約1,600円高くなっています。
対処法
まずは、暖房や冷房といった大口の電気消費源の対策をしましょう。
特に重要なのがエアコンの清掃です。フィルターがほこりなどで目詰まりしていると、電気代が必要以上にかかります。
また、家に太陽光発電やオール電化を導入するなどして、輸入燃料に頼らない発電方法を検討するのも重要です。
2022年(令和4年)の12月、東京都において、新築住宅への太陽光パネルの設置を義務とする条例が成立しました。これを受け、太陽光発電が設置された住宅は一層、住宅としての価値が高まることが考えられます。
食費が上がる
農林水産省は、2021年(令和3年度)の食料自給率を38パーセントと発表しました。
食料品のほとんどを輸入に頼っているわけですから、円安では食費が上がります。特に影響を受けるのが、小麦製品(パンやうどん、お菓子など)や食用油、動物性タンパク質(肉、卵、乳製品)、外食費などです。
対処法
円安でも比較的値上がりしにくいのが、米や野菜、魚介類です。
献立を決める際は、これらの食材を利用することで、食費の上がり方を抑えられます。
さらに、よく使う調味料(しょうゆや塩、砂糖など)は安いときに買いだめしておく、家計簿をつけるなどの対策も、細かいようですが効果的です。
賃金が下がる場合もある
円安では、社会全体の物価が上がります。仕入れのコスト増加や消費者の買い渋りから、業績が下がってしまうおそれがあります。
この結果、賃金が下がってしまう方もいます。また、物価が上がったことによって、賃金そのものは下がっていなくとも、実質的に購入できる商品が少なくなること(実質賃金の低下)も起こり得ます。
対処法
無駄な出費を抑えることが重要です。家計簿をつけたり、FP(ファイナンシャル・プランナー)などの「暮らしとお金に役立つ資格」などを取得して、収入と支出のバランスを整えましょう。
また、物価の上昇であまり価値の変わらない資産(株式や金など)の購入や売却もおすすめです。
特に「不動産」は、先ほどお伝えした通り、円安の今だからこそ売り手市場が形成されています。買い抜けやすく、利益が出しやすい状態です。
不動産を売却して売却益を得たい方、不動産投資をしたい方は、不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」をお試しください。
リビンマッチは、相見積もりで不動産の価値を確認できる完全無料のサービスです。売却益を増やすには、できるだけ多数の不動産会社に売却価格を査定してもらい、高値をつけてくれる会社、売却活動を積極的にしてくれる会社を選ぶ必要があります。
妥協して不動産会社を選ぶより、複数社を比較検討することでよりよい会社に売却を仲介してもらいやすくなるためです。よりよい会社に売却を依頼できれば、高い売却益が期待できます。
最大6社の不動産会社の売却価格を確認できるリビンマッチを利用して、円安のメリットを享受しましょう。
おすすめ記事:
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
編集してください:リビンマッチでは不動産売却や賃貸管理、土地活用をはじめとする不動産取引をサポートするサービスを提供しています。また、複雑な不動産取引をわかりやすく解説し、利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。不動産取引でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひリビンマッチをご利用ください。
コンテンツの引用ルール運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
マンション売却 (133) 戸建て売却 (107) 注意点 (102) アパート/マンション経営 (61) メリットとデメリット (55) 価格 (54) 税金 (52) 不動産会社 (51) 基礎知識 (50) コツ (49) 相続 (47) 土地売却 (44) ローン (42) 費用 (41) マンション管理 (41) アパート管理 (40) 住み替え・買い替え (39) 手順 (29) 売買契約 (29) トラブル (28) 相場 (27) 査定 (24) リスク (23) ポイント (23) タイミング (22) 一括査定サイト (21) 建築 (20) インタビュー (19) 空き家 (19) 確定申告 (17) 移住 (16) 譲渡所得・損失 (14) 控除 (14) 書類 (13) 賃貸併用住宅 (13) 仲介手数料 (12) 競売 (12) 期間 (12) 媒介契約 (11) 共有持分 (11) 利回り (10) 種類 (9) 抵当権 (9) リフォーム (9) 保険 (7) 空室対策 (6) 登記 (6) 資格 (5) 工法 (5) 選び方 (5) 節税・減税 (5) 不動産投資 (1) 資金調達 (1) 老後 (1) 生活保護 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用する際は、引用元が「リビンマッチ」であることを明記してください。
引用ルールについて














