【図解あり】不動産売却の流れをわかりやすく解説
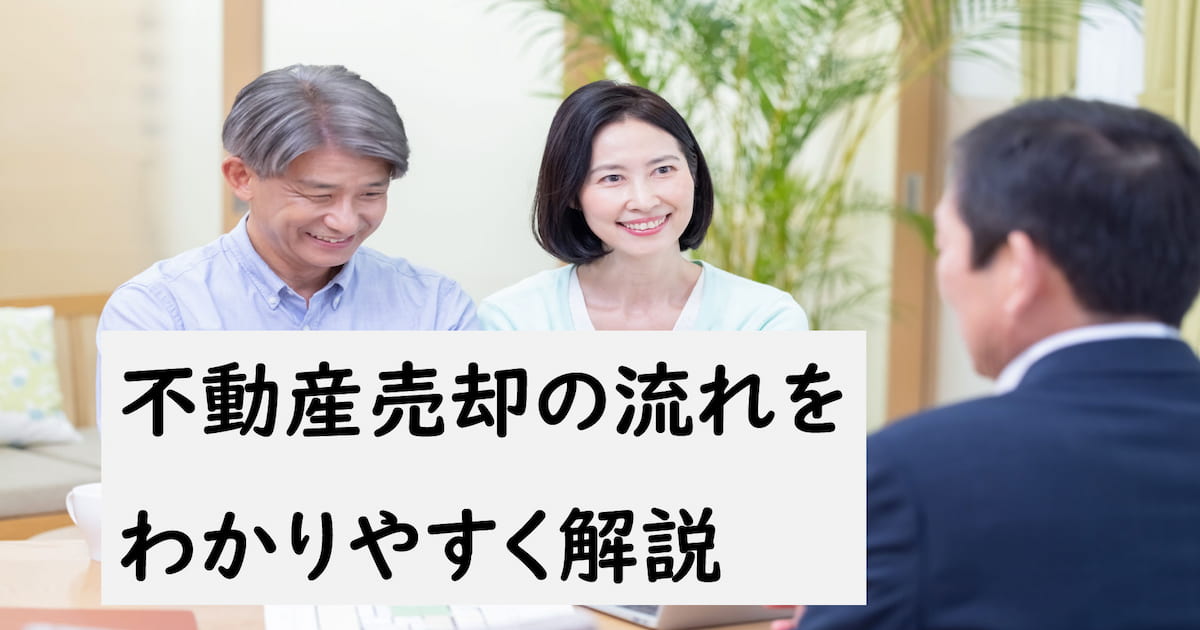
不動産を売却しようと思ったとき、何から始めればよいのでしょうか。また売却にはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。 不動産売却の流れや各工程での注意点などをわかりやすく解説します。
もくじ
不動産売却の流れを理解すべき理由
不動産売却の流れを理解することには、多くのメリットがあります。
正しい知識にもとづく決定ができるようになる
売却の際には、不動産会社や司法書士などの専門家に相談する機会があります。自分自身でも売却の流れを理解しておくことで、正しい知識にもとづいた決定を行えます。
不動産会社や専門家とのコミュニケーションがスムーズになる
不動産会社や専門家とのコミュニケーションにおいても、自分が売却の流れを理解していることで、スムーズなコミュニケーションが行えます。
売却にかかる期間や費用を予測することができる
不動産売却には、物件の状態や価格帯によって売却期間や売却にかかる費用が異なります。売却の流れを理解することで、物件の状態や価格帯に応じた売却期間や費用を把握できます。そのため、自分のスケジュールや予算に合わせた売却計画を立てられます。
不動産売却の流れを図解
不動産売却は以下のような流れで進めていきます。売却にかかる期間は不動産会社に相談してから、引き渡しまでに約3〜6カ月です。

不動産売却の流れ(図解)
各工程の詳細と注意点を詳しく紹介します。
【STEP01】不動産会社へ査定依頼
まずは不動産会社に査定依頼をします。査定とは、不動産がいくらで売れるのかを不動産会社に評価してもらうことです。査定依頼をしたからといって必ず売却しなければいけないことはありません。査定は無料であるため、まずは相談もかねて複数の不動産会社に査定依頼をするとよいでしょう。
査定方法の種類
査定方法には「訪問査定」と「机上査定」の2種類があります。それぞれの違いを押さえておきましょう。
訪問査定
訪問査定は、不動産会社が物件や周辺環境を確認し、査定価格を算出する方法です。担当者が物件を内覧するため精度が高く、実際の売却価格に近い査定価格がでます。 ただし、訪問査定は正確性が高いものの、査定結果が出るまで約数日〜1週間かかります。
机上査定
机上査定は、物件の図面や類似物件の売却事例などから査定価格を算出する方法です。早ければ当日、遅くても数日以内には査定結果がわかりますが、精度の面では訪問査定に劣ります。
不動産査定は一括査定がおすすめ
不動産の査定を依頼するときは、一括査定サイトを利用しましょう。一括査定サイトは、インターネット上で複数の不動産会社に査定を依頼する方法です。基本的には机上査定ですが、希望すれば訪問査定も受けられます。一括査定には以下のようなメリットがあります。
- 複数の不動産会社を比較できる
- 問い合わせが一回で済むため手間がかからない
- 相場感がつかめる
まずは一括査定により複数の不動産会社を比較検討しましょう。そして、候補となる不動産会社に訪問査定を依頼して、じっくりやり取りをするのがおすすめです。
査定価格は高ければよい?
複数の不動産会社に査定依頼をした場合、高い査定価格を提示した会社に魅力を感じるかもしれません。しかし、査定価格は高ければ高いほどよいというわけではありません。本来の価値より高い査定価格を提示して媒介契約を結ぼうとする不動産会社もいるためです。
不動産会社を選ぶときには、提示された査定価格と相場を比較して見極めるようにしましょう。
【STEP02】媒介契約の締結
不動産会社が決まったら、次は媒介契約を結びます。媒介契約にはいくつか種類があるため、自分に合ったものを選びましょう。媒介契約の種類と、選び方について解説します。
媒介契約の種類
媒介契約は以下の3種類あり、それぞれの違いは以下のとおりです。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数者との契約 | ○ | × | × |
| 自分で買主を探せるか | ○ | ○ | × |
| 指定流通機構(レインズ)への登録 | ×(任意) | ○(7日以内に登録) | ○(5日以内に登録) |
| 業務状況の報告義務 | ×(任意) | ○(2週間に1回以上) | ○(1週間に1回以上) |
| 不動産会社の責任度 | ★☆☆(低) | ★★☆(中) | ★★★(高) |
| 売主の自由度 | ★★★(高) | ★★☆(中) | ★☆☆(低) |
不動産会社の責任度が高い契約ほど積極的な売却活動が期待できます。その反面、ほかの不動産会社と契約を結べない、自分でよい買主を見つけても売却ができないなど、売主の自由度は低くなるため、売却の幅が狭まるという点はデメリットといえるでしょう。
媒介契約を結ぶ際の注意点
3種類の媒介契約はどれもメリット・デメリットがあり、どれがよいとは一概にはいえません。自身が売却活動に割ける時間などによって、適した契約を選びましょう。
売却活動を不動産会社に任せたい場合は専属専任媒介契約や専任媒介契約、自分でも動きたい場合は一般媒介契約が向いています。また、いずれの契約を選ぶにせよ、不動産会社とは密に連絡を取り、進捗状況を常に把握する姿勢が重要です。
【STEP03】売却活動
不動産会社と媒介契約を結んだら、いよいよ本格的な売却活動に移ります。売却活動を行う際に、売主が気をつけるべきポイントについて解説します。
売却活動の方法
基本的に売却活動は不動産会社が行います。どのような活動をするかは会社によって異なりますが、多くの場合以下のような方法で購入者を募集します。
- レインズへの登録
- ポータルサイトやホームページへの掲載
- 新聞の折り込みチラシやポスティング
- 自社の顧客に紹介
レインズとは、不動産会社が閲覧できる物件流通サイトのことです。ポータルサイトは誰でも閲覧ができるスーモやホームズなどを指します。有効な売却活動はエリアやターゲット層によって異なります。不動産会社がどのような方法で売却活動を行うかを確認しておきましょう。
売主がするべきこと
売却活動は不動産会社に任せられますが、売主自身も努力することで、物件をより早く、より高く売却できる可能性が高まります。売却活動時に売主ができることを紹介します。
部屋の掃除
物件の購入希望者は、基本的に内覧を行います。そのときに部屋が汚れていたり、設備が壊れていたりすると悪印象を抱かれてしまいます。内覧の前には、掃除や換気をして、清潔な状態を保ちましょう。また、壊れている設備は修理・交換を行い、内覧をしたあとに購入意欲が高まる工夫が重要です。
レポートの確認
専任媒介契約、専属専任媒介契約は、売主へ定期的なレポートの提出が義務付けられています。レポートが送られてきたら必ず目を通し、疑問点は質問しましょう。売主が積極的に売却活動に関わって売却したい意思を示すことで、不動産会社も売却活動をより積極的に行ってくれるでしょう。
【STEP04】買主と売買契約の締結
購入希望者が現れ、融資の審査がおりたら、売買契約の締結に進みます。契約締結時は売主と買主、どちらか(もしくは双方)の不動産会社が集まり、重要事項説明や契約書の確認が行われます。 内容に問題がなければ、契約を結びます。
契約書や各種書類に署名、捺印し、買主から売主に手付金が支払われます。仲介手数料もこのタイミングで支払われるケースがほとんどです。 一度契約を結ぶと、撤回することはほぼ不可能です。特に以下2点に留意して、慎重に契約を結ぶようにしましょう。
- 契約時の書類をしっかり確認する
- 契約不適合責任
契約時の書類をしっかり確認する
売買契約時には、「売買契約書」と「重要事項説明書」が作成されます。
- 売買契約書
- 売買代金や支払日、契約違反時の解除などといった、取引に関する内容が記載された書類
- 重要事項説明書
- 対象物件に関する事項が記載された書類。具体的には、飲用水・電気・ガスなどのライフラインの整備状況や、道路の種類・制限といった内容が盛り込まれている
契約時には、まず重要事項説明書を用いて宅地建物取引士(不動産会社)が重要事項の説明を行い、売主・買主双方合意のうえ売買契約を結びます。
書類には専門用語も多く出てくるため、不動産会社に任せきりで合意、契約が進むことも少なくありません。しかし、契約後にトラブルが生じた場合、売主が法的責任を負うこともあります。トラブルを回避するためにも、疑問点や不明点があれば、必ず解消してから契約を結びましょう。重要事項説明書や売買契約書は事前に確認することも可能なので、不動産会社に相談するとよいでしょう。
契約不適合責任
契約を締結したあとは、原則として撤回できません。契約締結後に齟齬が生じると、売主は法的責任を負う場合があります。特に売主が注意したいのが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、売却した物件が契約内容に適合していなかった場合、売主が負う責任を指します。2020年4月より「瑕疵担保責任」から改められたため、まだ聞き馴染みがないという方も多いかもしれません。
契約書に記載されていない買主にとって不利な状況(建物の瑕疵や権利の制限など)があった場合、契約不適合責任により買主から建物の修理や代金の減額、損害賠償、契約解除などを追及されるおそれがあります。
特に中古住宅を販売する場合は、汚損や老朽化が見られる部分については細大漏らさず契約書に記載しなければなりません。
【STEP05】決済と引き渡し
売買契約の締結から実際に決済・引き渡しが行われるまでの期間は約1〜2カ月です。買主・売主ともに、決済に必要な書類や資金の準備をするため、すぐに売却できるわけではありません。
買主は、この段階になって初めてローンの本審査を受けられます。問題なく融資がおり、ほかのトラブルもなければ決済・引き渡しが行われます。決済・引き渡しの流れと、注意すべき点を紹介します。
決済・引き渡しの流れ
決済は買主が指定した場所で行われます。売主、買主のほかに不動産会社、買主に融資をした銀行の担当者、司法書士が同席します。また、ローン残債がある場合は、売主側の銀行の担当者が立ち会うこともあります。決済当日の流れも押さえておきましょう。
書類の確認
司法書士が買主・売主双方の本人確認と所有権移転登記にかかる書類の確認を行います。
金銭の授受
買主から売主へ、手付金を差し引いた残額が支払われます。固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金などの支払いも行われます。金銭の授受が完了したら、売主は買主に領収書を発行します。一般的には、不動産会社が準備します。
同時決済も可能
ローンが残っている不動産は銀行が抵当権を持つため、第三者に売却ができません。抵当権を抹消するためには、ローンを完済する必要があります。預貯金で返済できない場合は、決済時に買主から支払われた代金で支払う「同時決済」も可能です。
同時決済を行う場合は、あらかじめ銀行に連絡して、抵当権抹消書類を準備してもらう必要があります。時間がかかるため、契約締結後速やかに銀行に連絡しましょう。
【STEP06】売却価格によっては確定申告が必要
決済・引き渡しが終われば売却は完了ですが、そのあとで忘れてはならない手続きが確定申告です。売却益があるにも関わらず確定申告をしていないと、追徴課税を要求されるおそれがあります。必ず決まった期日までに申告しましょう。
確定申告のタイミングと手続き方法
不動産売却にかかる確定申告は、売買取引が成立した翌年に行います。申告の時期は2月16日〜3月15日となるため、遅れないようにしましょう。確定申告には、以下の書類が必要です。自分で用意する書類も多いため、不動産売買で取得した書類は必ず保管しておきましょう。
| 書類 | 取得元 |
|---|---|
| 確定申告書B様式 | 税務署から取得 (ダウンロードも可) |
| 譲渡所得の内訳書 (確定申告書付表兼計算明細書) | |
| 不動産購入時の売買契約書 | 自分で用意する |
| 不動産売却時の売買契約書 | |
| 仲介手数料や印紙税など、売却費用の領収書 |
確定申告書の作成や作成に必要となる所得の計算は煩雑であるため、まとまった時間がとれない方は税理士に依頼しましょう。
不動産売却は余裕のある計画を!
ここまで不動産売却の流れについて紹介しました。売却の相談をしてから引き渡しまでは約3~6カ月かかりますが、この期間は物件の状態や売り出し価格によって差があります。これは、不動産取引は買主が存在して初めて売買取引が成立するからです。
買主がまったく現れなかったり、売買契約直前でキャンセルされたりすると1年以上売れないケースもあります。そのため、売却活動には余裕のあるスケジュールを立てましょう。
これから、売却を検討している方は一括査定サイトのリビンマッチを利用しましょう。簡単な入力をするだけで、複数社へ査定依頼ができます。査定価格や担当者の対応を比較検討することで、満足のいく不動産売却ができるでしょう。
関連記事
- 不動産売却の平均期間は?売却スケジュールやタイミングも併せてご紹介
- 家の売却に必要な平均期間は6カ月!期間が長引く売れない物件の特徴とは
- 不動産売却の引き渡し日の流れ!トラブル回避法についても紹介
- 不動産売買における重要事項説明の目的と要点を分かりやすく紹介
- 家の売却時に必要な準備を初心者にもわかりやすく紹介
- 不動産を売却しやすい時期はいつ?会社選びが重要な理由
- 住み替え時に利用したい引き渡し猶予とは?売主にもリスクがあるって本当?
- 【初心者必見】家を売る前にすること・やってはいけないことを徹底解説!
- 売買契約とは?締結の流れと必要書類や契約解除について解説します。
- 家が売れてからお金が入るまでの期間は?取引全体のお金の流れや注意点を解説
- 家を売るとき、いつまで家に住める?引き渡し日を延ばす方法はある?
- 家の売却を成功させる内覧の流れを解説。購入意欲を高める準備と対応とは

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わったのち、2021年よりビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。自身がマンション好きであるため、特にマンションに関する記事制作が得意です。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
編集してください:リビンマッチでは不動産売却や賃貸管理、土地活用をはじめとする不動産取引をサポートするサービスを提供しています。また、複雑な不動産取引をわかりやすく解説し、利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。不動産取引でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひリビンマッチをご利用ください。
コンテンツの引用ルール運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
マンション売却 (133) 戸建て売却 (107) 注意点 (102) アパート/マンション経営 (61) メリットとデメリット (55) 価格 (54) 税金 (52) 不動産会社 (51) 基礎知識 (50) コツ (49) 相続 (47) 土地売却 (44) ローン (42) 費用 (41) マンション管理 (41) アパート管理 (40) 住み替え・買い替え (39) 手順 (29) 売買契約 (29) トラブル (28) 相場 (27) 査定 (24) リスク (23) ポイント (23) タイミング (22) 一括査定サイト (21) 建築 (20) インタビュー (19) 空き家 (19) 確定申告 (17) 移住 (16) 譲渡所得・損失 (14) 控除 (14) 書類 (13) 賃貸併用住宅 (13) 仲介手数料 (12) 競売 (12) 期間 (12) 媒介契約 (11) 共有持分 (11) 利回り (10) 種類 (9) 抵当権 (9) リフォーム (9) 保険 (7) 空室対策 (6) 登記 (6) 資格 (5) 工法 (5) 選び方 (5) 節税・減税 (5) 不動産投資 (1) 資金調達 (1) 老後 (1) 生活保護 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用する際は、引用元が「リビンマッチ」であることを明記してください。
引用ルールについて





















